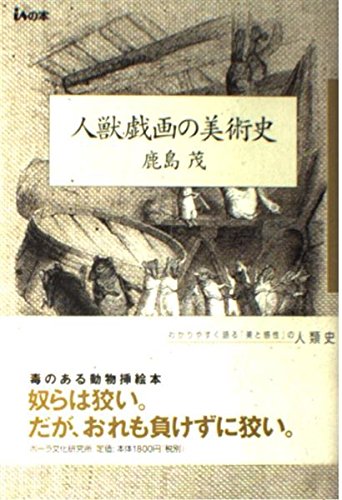鹿島茂『人獣戯画の美術史』という本を読んだ。ひと昔前の本を近所の古本屋で見かけ、曲がりなりにもケモナーを自称しているのだから読んでおこうと思った次第。
絶対王政期のフランスのモラリスト、ラ・フォンテーヌの『童話』を足がかりにしながら、19世紀のフーリエ主義者(マルクス主義登場以前の社会主義者の一派)であるアルフォンス・トゥスネルという思想家が唱えた「情念動物学」という(現在から見れば)トンデモな学説を半ばツッコミながら半ば真剣に紹介するという、いかにも鹿島茂的な本で、読み物としても面白い(遅読の自分が半日足らずで読了するのだからそれは間違いがない)。
「情念動物学」、突飛な思想ではあるのだが根底にある考えは興味深い。人間と動物に性格的類似性を見てとるという考え方は古来あったものではあるが、これがトゥスネル(もとい師匠のフーリエ)の場合は少し変わっていて、人間・動物ともに「動物性」というものを持っていて、動物にはその「動物性」をいっそう色濃く見て取ることができるという。そこまではいいとして、ならば動物を観察しその性質を調べ上げてしまえば、人間のこともわかったも同然である、なぜなら両者とも「動物性」を持っているという点では同じだから、と言い切ってしまうところが面白い。動物を通じて、そのまま人間を理解しようとする学問(?)である「情念動物学」。鹿島の記述を読む限りでは、実際のところは人間の性質を動物に当て嵌めているように見えなくもないし、奇書特有の謎論理に支配されてはいるものの、そこで描写されている動物の姿はケモナー的には興味深い(俗に言う「歓喜」とはまた違うのだが)。
この本のもう一つの肝(というか鹿島が一番喋りたいこと)は、本文中でたびたび図版が掲載されている挿絵画家J.J.グランヴィルだ。先日ケモナーたちのあいだで話題になっていた『鳥類弁護士の事件簿』のキャラデザの元ネタにもなった19世紀の画家である。1章ほどページを割いてグランヴィルについて語られていたのだが、それを読んでいくとなぜあのゲームでグランヴィルの『動物たちの私生活・公生活情景』が引用されたのか、というのが見えてくる。グランヴィルの動物挿絵がいかに画期的であるか。それをラ・フォンテーヌ『寓話』に載せられた挿絵の変遷を辿りながら解説される。最初期の挿絵は登場する動物たちは本物の動物としてごく普通に表象されていたのが、グランヴィルはそこに奇想を加える。人間の服装を見にまとい、二本足で立ち、しかし姿は動物、そのような生き物として表現したのである。
「動物であって動物ではなく、人間であって人間でない」そういう「人獣」という概念が、グランヴィルの挿絵とともに現れた。「人獣」はケモナーの考える「ケモノ」の概念にかなり近い存在と言えるだろう。実際『寓話』の挿絵も、グランヴィル以降こうした「人獣」的な描写が主流になっていく(同時代のギュスターヴ・ドレもやはりグランヴィルの影響を受けているのだという)。彼の挿絵は、動物表現におけるコペルニクス的転回だったのである。その想像力を支えていたのが人間と動物に共通した「動物性」を見出すフーリエの特異な思想であった……ということで全ての話が繋がるのだ。
本書で取り上げられたトゥスネルの思想やグランヴィルの動物挿絵の源流にあるフーリエの『四運動の理論』を、今後ケモノ文学という文脈から読み解くのも面白いのではないか……とこれもまた突飛な思いつきであるけれど、頭の片隅にでも留めておこうか。